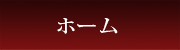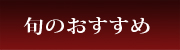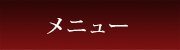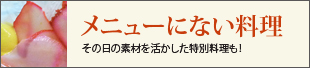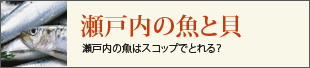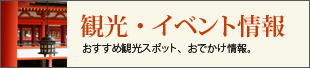■カサゴ(赤メバル)の煮付け
■カサゴ(赤メバル)の煮付けカサゴは晩秋から翌年の春にかけてが美味しい。特に瀬戸内産のカサゴは身が締まり、脂ものって美味しい。
煮付けがおすすめだが味噌汁、塩焼き、唐揚げで食べても美味しい。
 ■ミズガレイの塩焼き
■ミズガレイの塩焼き正式名はムシガレイで旬は秋〜春。身質は透明感のある白身で塩焼きにするとふんわりとした食感で、上品な味わいを楽しめます。
鮮魚を塩焼きで食べる他に、唐揚げや一夜干しにしたものを焼いて食べても美味しい。
 ■ウミタナゴの煮付け
■ウミタナゴの煮付け沿岸の岩礁などで群れをなして生息し、卵でなく仔魚を産み出す、ちょっとめずらしい習性の魚。南蛮漬けや唐揚げなどで楽しめますが、やっぱり脂ののったタナゴを煮付けで食べたいですね。
 ■秋刀魚の刺身
■秋刀魚の刺身秋はやい時期は新鮮なものを、刺身で食べたい。魚好きにはたまらない味です。秋が深まり脂がのったサンマは丸ごと焼いて大根おろしで。サンマには、血液の流れを良くするといわれるエイコサペンタエン酸が多く含まれており、脳梗塞などの病気を予防する効果があるといわれています。
 ■カボチャの天ぷら
■カボチャの天ぷらカボチャは夏野菜ですが食べごろは秋。収穫後、水分が抜けて甘味が増すこの時期が食べごろです。きつね色に揚げたカボチャの天ぷらは、サクサク、ホクホク!たまりませんね。動脈硬化予防にもいいみたいです。
 ■ワチの焼きびたし
■ワチの焼きびたし正式名はサッパ。岡山ではママカリとよばれ、名物料理になっています。うろこと内蔵を取ったものを焼いて焦げ目をつけたものを、熱いうちに三杯酢に漬けたものです。思ったよりコクがあって、美味しいです。
 ■太刀魚の塩焼き
■太刀魚の塩焼き秋口にはかなり脂が乗ってきて、塩焼きやバター焼き、刺身で食べると甘みがあって美味しい。特に皮と身の間に旨みの詰まった脂がある。良質な脂肪酸やDHA、オレイン酸などもを多く含んでおり、積極的に食べたい食材です。
 ■焼きしいたけ
■焼きしいたけしいたけのおいしい季節は春は3~5月、秋は9~11月です。
しいたけはとても低カロリーでビタミン、ミネラル、食物繊維も豊富に含んでいます。肉厚の焼きしいたけにすこし醤油をたらし、かぼすなど搾って食べる。旬の時期ならではの味わいです。
 ■銀杏
■銀杏塩で炒った銀杏は、もちもちとした食感と、ちょっとした苦みがあっておいしい。ひすい色のおいしさ!といったところですか!?銀杏は糖質、ビタミンB1、カリウム、カロチンなどの栄養が多く疲労回復、老化防止にも効果があるそうです。積極的に食べたい食材ですね。
 ■チヌの塩焼き
■チヌの塩焼き釣り人にはお馴染みの黒鯛、秋から冬が旬。おもに刺身、塩焼き、煮付けなどで食べます。鮮度のいいものを丸ごと塩焼きにすると身がぷりぷりして絶品です。チヌ飯で食べる地域もあるようです。